結論
特別支援学校は、教員の数が多く教員と子供が関わる時間が多いです。1日の流れもゆっくりなので、自分のペースで過ごすことができます。特別支援学級は忙しくするべきことも多いですがその分得られる知識や経験は多いです。本記事は以下のお悩みを解消します。
- 特別支援学級について知りたい
- 特別支援学校について知りたい
- 支援学校と支援学級の違いを知りたい
- 支援学校と支援学級の1日に流れがしりたい
特別支援学校に勤めた経験

私は3年間特別支援学校で教員をしていました。1年目は特別支援学校小学部。2年目と3年目は、小学校の中に併設された特別支援学校で、『〇〇支援学校分教室』として2019年にできた学校でした。
つまり、○○小学校の校舎内に○○支援学校がつくられ、子どもたちは学校行事や給食などで交流を深めていくという学校でした。
私は、空いた時間に特別支援学級のサポートもしていたので、特別支援学校と特別支援学級の様子がわかります。その経験を生かして、特別支援学校と特別支援学級の違いを解説します!!
お子さんについて

特別支援学校と特別支援学級に通うお子さんについて解説します。
特別支援学校に通う多くのお子さんは、認知や知的水準は比較的重く、コミュニケーションが難しく日常生活面で多くの支援を要するお子さんたちが通う学校です。
しかし、できることとできないことがお子さんによって幅広く、個々に合わせた支援と指導が必要です。例えば、言葉によるコミュニケーションができるお子さんも通っていますし、発語がないためカードやジェスチャーでコミュニケーションをとるお子さんもいます。
一方特別支援学級では、日常生活面での支援が必要なことはあまりありません。もちろん、配慮事項があるお子さんが通われることもありますが、例えば排泄や着替えで支援が必要なことはほとんどないでしょう。
また、社会性や対人関係でトラブルが多かったり、習得している語彙などに差があったりするものの、意思疎通はスムーズにやり取りできるお子さんが多いです。
特別支援学校の特徴

行事が少ない
運動会や学習発表会、遠足、宿泊行事など大きな行事はありますが、小学校のように朝会や○○集会など全校で集まる機会は少ないです。
個別学習の時間
個別学習の時間では、子どもの実態に応じて認知機能を高める課題や手指の巧緻性を高める学習などを行うことが多いです。
例えば、ビーズをヒモに通したり、穴の開いた箱にビー玉を入れるなど作業課題に取り組みます。本当にお子さんの発達によって異なるので、ケースバイケースですが、読み書きや数字、時計の読み方などの学習するお子さんもいらっしゃいます。
作業療法士や理学療法士と連携している
身体の動きや認知機能などに詳しい専門家の先生が子どもの様子を観察し教員に課題の見直しや関り方をアドバイスします。
しかし、これらの専門家は必ずしも各学校に1人いらっしゃるわけではありません。年に数回派遣されてくる場合もあります。
子どもにつく教員の数が多い
特別支援学校では、1学級に6人までと決まっています。さらに、障がいが重複しているお子さんの場合は1学級に3人までです。
私の経験上、1学級お子さんが4人で教員2~3人や1学級子どもが6人で教員3人プラス1人補助の先生といった配置が多いです。そのため、支援学級よりも教員と関わる時間は確保されるでしょうし、怪我や個に応じた対応を取ってもらえます。
特別支援学校の1日
8:50 スクールバスが学校に到着
9:00 トイレや着替え、カバンの整理などを終えて遊び
9:15 1時間目 朝の会
9:45 2時間目 個別学習/自立活動
10:20 中休み
10:50 音楽/体育/図工/生活(学校により異なる)
11:35 遊び/自立活動
12:00 給食・昼休み
13:30 生活/音楽/体育/図工/個別学習/自立活動(学校により異なる)
14:15 帰りの会
14:30 下校
特別支援学級の特徴

同じ学年の子どもとの交流が多い
都市部の特別支援学級ではだいたい1クラス6~8人在籍しています。その中で同じ学年のお子さんは2~3人程度だと思います。また、通常学級の子どもたちとも活動する機会がたくさんあるので、お友達はできやすい環境です。
ただし、交流が好きかどうかは本人の気持ちにもよりますし、担任の力量も少なからず影響します。そのため、交流を嫌う子どももいますし、最初の頃は自然に打ち解けていたけれど、学年が上がるにつれて通常学級と一緒に活動することを躊躇し始める子どもも少なくありません。
行事が多い
大きな行事が、学習発表会(文化祭)、運動会、入学式、卒業式、遠足、社会見学、防災訓練です。これは、特別支援学校でも行われています。これらに加えて、小学校で行われる行事は基本的に全て参加します。
多くの小学校でよく行われている行事は、1年生~6年生までを混ぜたグループを形成し交流を深める行事を行っている学校も多いです。例えば一緒に給食を食べたり、6年生が遊びを企画して遊んだり、校内スタンプラリーを実施しているところもあります。
その他には、月始めの朝会、学力調査、体力テスト、縄跳び大会や持久走大会、音楽集会などがあります。また、4年生では音楽関連の行事を市単位で実施しています。
地域の特色を生かした授業を行っている学校も多いです。地域の方を招いて、地域の伝統的な遊びや文化に触れる授業が行われることもあります。私の知っているところでは、しめ縄作り体験を行っている学校やフィリピンの伝統的な遊びを知る授業を行っている学校がありました。
クラブ活動や委員会活動がある
こちらは、特別支援学校でも行われていることもありますが学校によります。一方小学校ではほぼ確実に行われる授業です。クラブ活動や委員会は、4年生から6年生のお子さんが参加する特別活動の学習として行われます。先生は枠組みを作る程度で運営のほとんどは子どもたちが主体となって行います。
通常学級で学ぶ科目が選べる
小学校の科目は、9科目あります。それらすべてを通常学級で受けている子もいますが、一部を選んで参加しているお子さんがほとんどです。科目選びは面談時に保護者と本人と相談して決定します。
宿題が出る
宿題は基本的に特別支援学級の担任から出されます。しかし、通常学級との交流が深ければ通常学級からも出ます。学力の補強という面ではメリットかもしれませんが、近年、共働き家庭が増えたことにより子どもに宿題をさせることがストレスになっている保護者の方もいらっしゃるようです。
また、なかなか自分で宿題を取り組むことが難しい場合もあるので、宿題が出ることがメリットと感じるかデメリットと感じるかは保護者の考え方によって大きく異なるでしょう。
教員が少ない
特別支援学級では、1クラス(1人の教員が)8人までのお子さんを見ることができるという法律があります。しかし、実際には1人で8人のお子さんを指導することは難しい状況です。
というのも、人間関係のトラブルが頻発したり、通常学級で授業を受けたいけど先生の付き添いがないと教室に入れないなどニーズが増えてきているからです。
もちろん、通常学級での学習は担任が見ることになりますが、通常学級の中でも支援を要するお子さんがいるのはもう当たり前です。そのため、十分な支援を行えないため交流が難しくなるケースもあるのです。
仮に特別支援学級に12人のお子さんが在籍しているとします。この場合、担任は2人態勢です。例えば、自分の気持ちをうまく伝えられずトラブルになる子が1人いれば、教員が1人対応します。
では、残りの11人がスムーズに学習できるかと言うとそのようなケースはほとんどないでしょう。集中力が続かない子もいますし、個別に学習を見ないと勉強についていけなくなるこもいます。そもそも、勉強に興味がなく教室を出ていく子どもも在籍しているかもしれません。
特別支援学級は慢性的な人手不足で、学習がおろそかになってしまうケースも目立ち始めています。
自治体の対策としては、有償ボランティアや地域の方のボランティア、学生ボランティアなどを広くボランティアを募集して補強しようと努めていますが、それもなかなか必要とするすべての学校に配置できるほどの人数は集まらないので課題が残ります。
人間関係でいろいろな経験ができる
通常学級や支援学級、他学年などたくさんの子どもたちと行事を通して関わることができます。お互いにぶつかり合うこともありますが、いろいろな経験を通して他人と自分を理解していきます。(のちに詳しく述べます。)
特別支援学級の1日
8:30 登校
8:45 朝の会
9:00 1時間目
10:20 中休み
10:50 3時間目
11:35 4時間目
12:20 給食・昼休み・掃除
13:30 5時間目
14:15 6時間目
15:10下校
人間関係の形成について
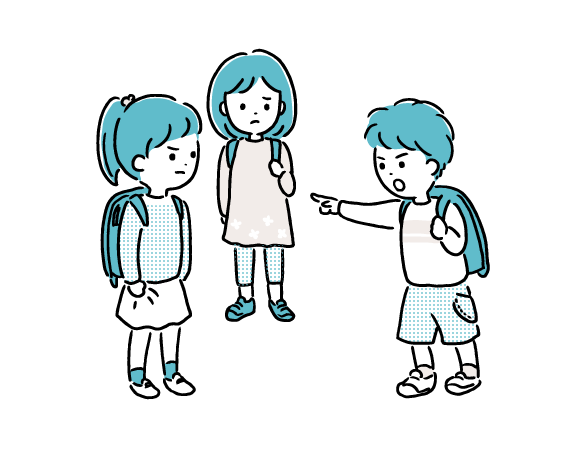
人間関係の形成、つまり友だち関係でも支援学校と支援学級では大きく違いがあります。支援学校では、1クラス6人までと小規模の学級になります。また、子ども同士のコミュニケーションよりも子どもと先生とのコミュニケーションがメインになります。どうしても発達段階的に子ども同士のコミュニケーションが難しいことが多いため、教員が意図的に授業で子ども同士の関わりがもてるように工夫をしています。
一方特別支援学級では、支援学級内でも通常学級内でも友だちと一緒に遊んだり授業に関する会話をしたりします。たしかに、対人関係や社会性が未熟でトラブルが多くなる傾向はありますが、それらを含めて成長していきます。低学年のうちは、国語や算数、生活など体験的な活動を通して学習をすることが多いので交流が盛んです。
支援学級でも、通常学級でもそれぞれの環境で対人関係や社会性を経験しながら身に付けられるのは、支援学級の良い点かもしれません。
しかし、全ての子が通常学級になじめるとは限りません。先ほども述べましたが、支援学級内や通常学級内で対人関係で様々なトラブルが考えられます。表現力の乏しさから暴言暴力、泣くなど激しい感情表現になってしまうこともあります。
また、学年があがって周りはスキンシップが減ったり、冗談の内容がより高度になってくると、情操的な発達がゆっくりなお子さんの場合、周囲と溝ができてしまうことが大変多いです。もちろん、教員はそのことを理解して双方を指導しますが、お互いに受け入れられないということもあるのです。
これが、学年があがるにつれて通常学級へ行く機会が減る原因の1つです。
居住地交流(副籍)について

特別支援学校では、年に3~4回程度ではありますが、お住いの学区の子どもたちと交流できる制度があります。これを居住地交流や副籍交流と呼びます。
保護者が希望すれば、担任が子どもが住んでいる学区の小学校の児童支援コーディネーター、もしくは特別支援コーディネータ―と連絡を取って交流する段取りを整えてくれます。
この居住地交流では、保護者の要望を基に担任と相手校の教員で交流の計画を立てるのでどのような交流を望むのかしっかりと伝えましょう。
もちろん、居住地交流を希望するかどうかのプリントが配布されるはずなので、そのプリントを基に次のことを伝えておくとよいと思います。
- 交流するのは通常学級か支援学級か。
- どんな授業で交流したいか。(多くのご家庭は音楽の授業と給食を一緒に食べる交流を希望されます。他にも体育や低学年なら生活の学習は参加しやすいかもしれません。)
- 保護者はつきそうかどうか。
迷ったらどうすればよい?

お子さんの発達段階を見たときにどちらが良いのか迷うこともあるでしょう。その場合、教育委員会の特別支援センターに問い合わせてください。就学先の決定に関して親身に耳を傾けてくれます。また、学校見学会も参加するとよいでしょう。
今回ご紹介したのは一部なので、地域や学校によって雰囲気や取り組みが全然違うこともあります。ぜひ、学校見学に参加してみてください。
特別支援学校か特別支援学級か迷われた場合、1つの基準は集団生活になじめそうかどうかです。特別支援学級は小学校の生活リズムと同じなので、様々な行事やイベントがあります。そして、支援学級と通常級をいったりきたりと忙しい毎日となります。
もちろん、先生方は全力でサポートしてくださりますが、どうしても対人関係のトラブルが相次いだりやだんだん通常学級のお子さんたちとうまが合わなくなるケースが多いということも事実です。
それらを一つの経験としてとらえられるかどうかは是非ご検討していただく際の重要なポイントとなると思います。

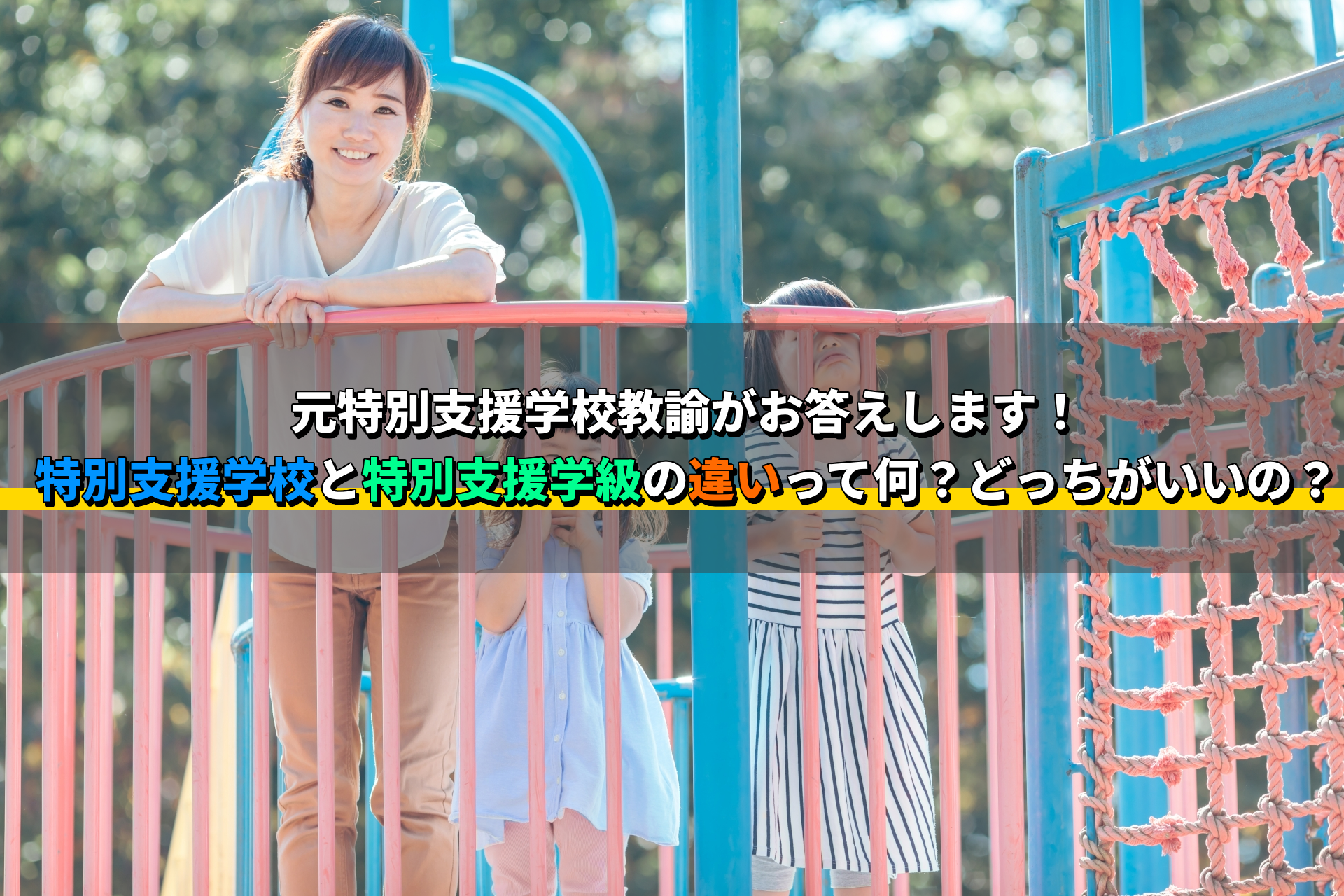
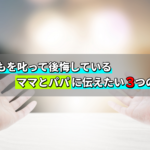
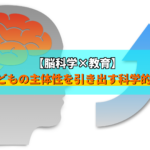
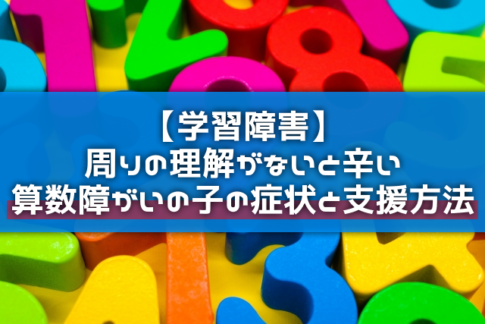

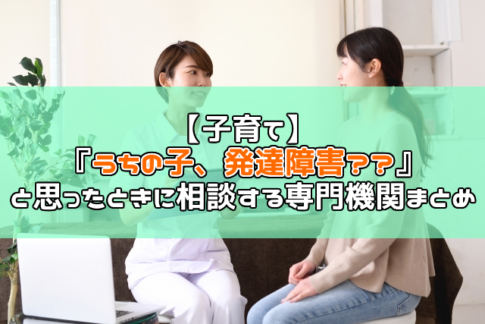
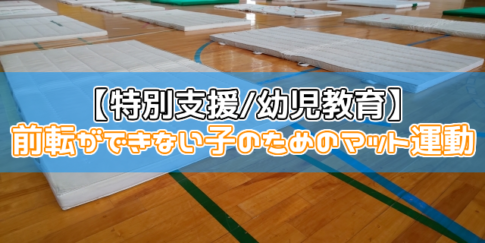
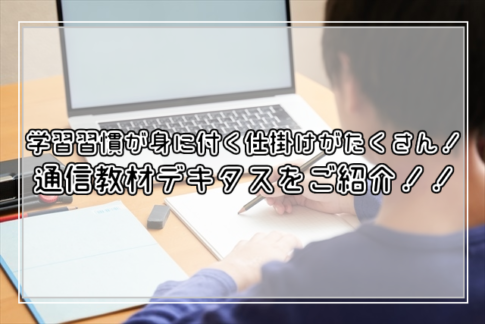
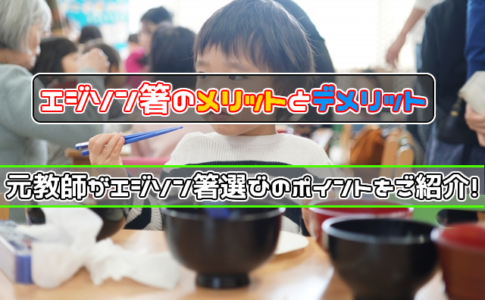
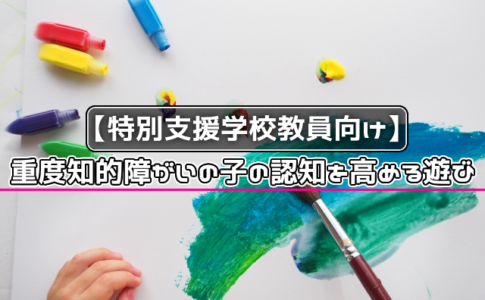
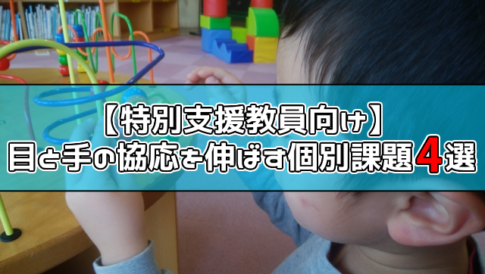


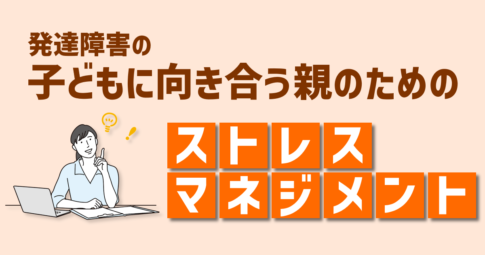
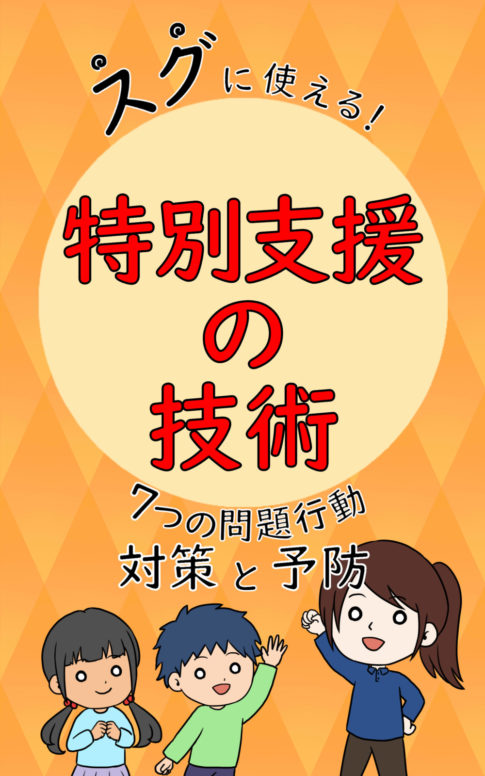






コメントを残す